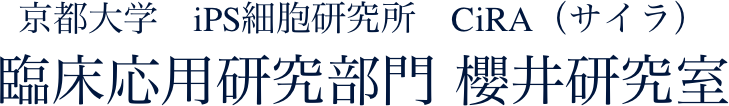

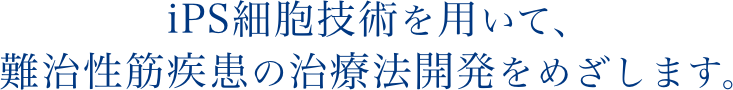
はじめに
_私たち櫻井研究室は、京都大学iPS細胞研究所の臨床応用研究部門を構成する研究室のひとつです。臨床応用に向けた研究・技術開発を行う部門の中で、私たちの研究室は難治性筋疾患に対する新たな治療法の研究を行います。
_ラボが立ち上がって15年目となり、臨床応用に近い研究成果を二つ成果発表できました。
_一つ目は、デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)に対する細胞治療法の開発の中で、細胞移植によってジストロフィンの発現が回復すると、いったいどんな治療効果が表れるのか?という点を研究した成果です。これまでの海外の研究室からなされている報告では、最大筋収縮力が上昇するという報告が多いのですが、我々の研究室でDMDモデルマウスを麻酔で眠らせて生きている状態で解析すると、最大筋収縮力はほとんど変わらないという結果を得ていました。我々は、この現象は治療効果がないのではなく、治療効果を判定する測定法が他にあるのではないかと考え、過去の様々な報告を参考に「運動後の疲れやすさ」について詳しく調査しました。すると細胞移植3か月後から効果が見え始め、4か月後には運動後にもパフォーマンスが落ちないようになりました。この成果により、臨床研究に進んだ際に患者さんの「疲れやすさ」を指標に治療効果を判定したほうが良いだろうということが分かりました。
_二つ目は、ウルリッヒ型先天性筋ジストロフィー(UCMD)に対する細胞治療法の開発の中で、6型コラーゲンを発現するiPS細胞由来間葉系間質細胞(iMSC)を移植すると治療効果があることを示してきました。6型コラーゲンは、iMSCに限らず、骨髄由来MSCや脂肪由来MSCにも発現しており、果たしてどのMSCが臨床応用に最適なのか不明でした。我々は健常ドナーから採取した骨髄由来MSCと脂肪由来MSCを用いてUCMDモデルマウスへの移植実験を進めました。またiMSCについても臨床応用可能な分化誘導培地を使って作製されたゼノフリーiMSCを移植して比較しました。その結果、6型コラーゲンの補充量は、どのMSCでも遜色ないのですが、肝心の筋再生促進効果はiMSCのみが安定して発揮していました。これはIGF2という成長因子の発現が高いことが重要ではないかと示唆されます。一方の骨髄由来MSCや脂肪由来MSCは移植された筋肉の中で線維化を起こしてしまうことが見受けられました。iMSCは全く線維化を起こさないため、有効性の上でも安全性の上でもiMSCが最も臨床応用に適した細胞であることが分かりました
_今年度から日本だけでなくベトナムや中国からもやる気のある若手が研究室に参加してくれました。臨床応用を目指した歩みを着実に進めていきたいと思います。
_研究内容などに興味がある方は、遠慮なくご連絡ください。
2025年7月 櫻井 英俊





